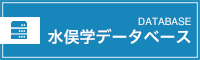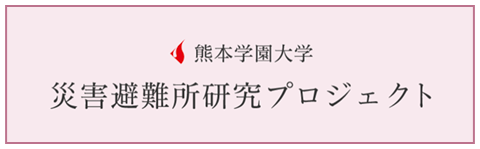2020年度
第1プロジェクト「水俣病被害の多面性に着目した問題解決のための包括的展望に関する研究」
【地域における被害調査】
患者聞き取りに関しては、研究員並びに水俣の客員研究員により継続的に実施されており、記録を積み重ねていった。さらに健康・医療・福祉相談事業を通した調査の遂行および胎児性水俣病に関する臨床的調査及び文献資料等の調査研究をすすめた。これまでのモノグラフィックな研究成果の研究会を重ねて突き合せ総合的に取りまとめ、被害の実態調査を継続した。
これらを通して、社会的にも、医学的にも、さらに法制度の面からも、多様な水俣病が浮かび上がってくることが予想され、被害の実態に即した補償・救済のあり方が明らかにされる。
【若い世代の患者ヒアリング:胎児性水俣病ワーキンググループ】
客員研究員を加えて構成されている胎児性水俣病ワーキンググループによる調査研究活動がベースとなって進められた。胎児性水俣病と同世代の若い患者(第二世代と称せられる)の水俣病に関して、2008年来検診、聞き取りをおこなってきているが、本年度も継続して行った。
胎児性世代の水俣病を取り巻く課題として、法制度的側面からの検討と病像と被害補償をめぐる問題の検討がある。これに関しては、主として大阪で水俣病訴訟の弁護団や阪南中央病院の医師グループらとの検討会を行い、行政の施策や資料の検討を実施してきた。これについては今後も継続される。
医学的検診には、下地明友(研究員)、井上ゆかり・田㞍雅美(研究員)があたった。ヒアリング作業および資料収集に当ったのは、花田昌宣、研究員の田㞍雅美・井上ゆかり、客員研究員の山下善寛・谷洋一・伊東紀美代・平郡真也らである。
本年度は、熊本で5回、水俣2回、大阪1回、オンライン17回、合計25回開催した。
【健康・医療・福祉相談】
現地研究センターにおける健康・医療・福祉相談事業は原田先生によって始められ、下地先生によって継続されている。被害の実態把握の研究調査活動の一環として位置づけるとともに、地元への社会的貢献として定期的に実施している。地元の被害者組織らと協力しながら進めている。本事業に寄せられる相談内容は、自身が抱える種々の症状が水俣病からくるものかそうでないのか、介護問題など多岐にわたる。また、相談者は不知火海沿岸住民(現在は関東や関西圏に居住する人含む)で、年齢層も様々である。
運営体制は下記の通りである。
医療担当:下地明友(客員研究員・顧問)
インテーク:田㞍雅美(研究員)、井上ゆかり(研究員)
事務局:福田恵子(水俣学研究センター事務職員)
協力者:鶴田和仁(潤和会記念病院名誉院長・客員研究員)、津田敏秀(岡山大学教授・客員研究員)、頼藤貴志(岡山大学教授・客員研究員)
開催数26回、累計40人であった。
【海外調査】
井上科研において、2020年度韓国、2021年度中国、2022年度カナダの公害発生地訪問調査が研究計画に盛り込まれ、このプロジェクトと連携して調査活動を行なっていくものであったが、2020年度は実施できなかったため繰り越し申請を行い文科省の承認を得たため2021年度以降実施する予定である。
これらは、2019年度開催した国際フォーラムで連携が深まった国々の研究者やNGOとの共同調査の実施に当てられる。
韓国については加湿器殺菌剤に関する研究センターがソウル大学に開設予定であり、2019年10月には水俣学研究センター長が国際疫学会で研究報告した折に訪問して、意見交換しており、ソウル大学との研究協力協定の締結が予定されている。
カナダについては、水俣病の発生が確認される先住民居留地への訪問調査を予定している。定期的な交流・交換が予定されており、先住民組織との公式的な関係を維持して調査研究を実施しているのは、カナダ国内以外では日本の本学のみであり、水銀汚染・水俣病の調査については水俣学研究センターが注目されている。
これらは、中間評価でも指摘された世界の途上国等での公害の調査と教訓の共有を念頭においた水俣学研究の国際的拠点としての基盤形成としての意義を有する。