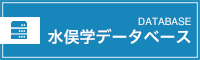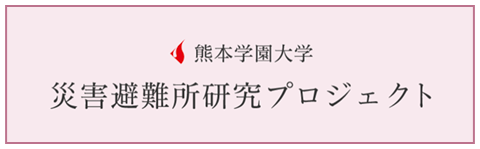第24回公開セミナー 第1回水俣学現地研究センターイブニングセミナー 「水俣の環境を考える」を開催いたします。
第24回公開セミナー 第1回水俣学現地研究センターイブニングセミナー「水俣の環境を考える」
◎水俣学研究センターは、水俣学現地研究センター開設以来、原田正純先生が提唱された水俣学を実践すべく、研究者と市民の協働で様々な研究活動やまちづくりの立案・参加を課題検討会として開始し、2010年から水俣、芦北地域戦略プラットフォームとして、研究会を連続して開催してきました。2017年1月第26回地域戦略検討会(第41回課題検討会)を最後に、中断したままです。
◎その後、2022年7月現地研究センター長に中地が就任したことを契機に、水俣・芦北在住の客員研究員に呼びかけて意見交換会を開催しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大や研究員の諸事情により、以前に比べて研究活動が停滞していたと反省しています。
◎その間、芦北から水俣、大口、出水の山間部に巨大風力発電の建設計画が具体化し、環境影響評価手続きが進行中です。大雨による水害や低周波騒音による健康被害の可能性、工事に伴う交通障害等の危険性と、発電したエネルギーをすべて大都会に送る計画は、水俣の地域づくりと相いれず、再生可能エネルギーだからと容認することはできないと考えます。
◎そこで、改めて、水俣・芦北の地域再生を考える研究会の開催について、下記の通り、第1回イブニングセミナーとして意見交換の場を持ちたいと思います。
◎つきましては、今まで、水俣・芦北地域プラットフォームに参加された方を中心に呼びかけさせていただきます。年度末でご多忙のおりですが、関心のある方のご参加をお待ちしております。◎◎◎◎◎◎日時:2024年3月18日(月)午後6時30分~8時30分
◎◎◎◎◎◎場所:水俣学現地研究センター2階会議室(水俣市浜町2-7-13)
◎◎◎◎◎◎内容:1.水俣学研究センターから問題提起
◎◎◎◎◎◎◎◎◎2.巨大風力発電計画の経過報告意見交換
◎◎◎◎◎◎◎◎◎3.意見交換☆準備の都合がございますので、参加される方は下記の水俣学現地研究センターまで、メール又はFAXでご一報いただければ幸いです。
☆お問合せ・お申し込み先
◎◎水俣学現地研究センター
◎◎◎◎〒867-0065 水俣市浜町2-7-13
◎◎◎◎TEL:0966-63-5030 FAX:0966-83-8883
◎◎◎◎e-mail:m-genchi@kumagaku.ac.jp
 市民向けの一般的な内容
市民向けの一般的な内容
今後の予定
以下は終了しました
研究活動報告
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業成果報告シンポジウム―水俣病の現在と水俣学の創造―を開催いたしました。
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業成果報告シンポジウム―水俣病の現在と水俣学の創造―を12月23日(月)熊本学園大学14号館1422教室で開催いたしました。
これまでの取り組みの概要とその成果や今後の課題について発表すると同時に、ご出席の皆様から忌憚のないご意見を頂戴し、第4期の研究センターの事業活動に活かしていきたいと考えて開催いたしました。
最初に花田センター長より、「水俣と水俣病の将来を構想する―水俣学研究の到達点―」として犠牲者非難の構図の転換の必要性を報告。田尻研究員は「健康・医療・福祉相談から見える水俣病被害の実態と施策の課題−被害者が求めるもの」とし、現地研究センターで行っている健康・医療・福祉相談から1968年以降生れにも水俣病の被害があり、幅広い年代の被害調査の必要性を報告。中地事務局長は「水俣の健康リスクと環境リスクを再検討する」とし、これまでの調査から水俣条約と水俣の汚染サイトの問題と課題を報告。藤本研究員は「水俣市円卓会議の経緯と ゼロ・ウェイスト政策」について報告。井上研究員は「水俣学アーカイブを活用した研究拠点形成に関する実証的研究−水俣の知的インフラの拡充に向けて」として大学で資料を保存・公開する意味、特徴、今後の課題を報告した。
参加者のアンケートには、「分かりやすく、豊富な内容であった。」、「時間が短かった。」、「水俣でも開催して意見交換をするとなお充実するのでは。」などのご意見を頂きました。
皆様のご意見を参考にし、今後も研究を進めていきます。