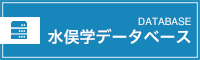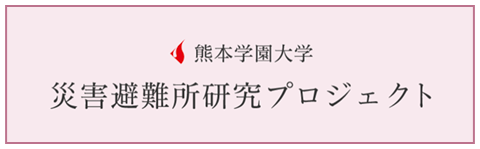2021年度
第一 水俣病被害の実態調査の継続
調査設計とレジリエンス評価手法の開発(花田昌宣)
現在、国や自治体によって水俣病に関連して進められているさまざまな被害者救済、地域振興策を資料に基づいて検討するとともに、自然生態系や環境汚染の変遷の全体像を資料に基づいて明らかにする作業を行った。
それに対する調査の手法、評価基準、実施体制に関する研究会がCOVID-19の影響により遅れているので集中的に行い、調査の具体的手段、方法を確定し、本年度夏から、まず水俣地域において調査を開始した。
・不知火海沿岸地域の漁村における生業調査と健康被害調査(井上ゆかり)(研究協力者:下地明友(医師・水俣学研究センター顧問・客員研究員))
漁村ごとに漁法も魚種も漁業形態も異なることに着目し、漁民の生業と健康被害の状況およびその連関を調査、被害の受容およびその社会的背景を明確にする。漁民の社会関与がレジリエンスの要素をなすからである。各種漁業資料と漁業者のヒアリングを重ねるとともに、研究協力者の参加をえて、臨床医学的な水俣病健康調査も行う。対象地区としては、水俣市、津奈木町および対岸の近海離島(御所浦)を予定していたが、先述したように感染状況や調査受け入れ状況などを鑑み次年度に持ち越すこととなった。
・健康と生活被害実態の検討(田尻雅美)(研究協力者:伊東紀美代(水俣病協働センター・水俣学研究センター客員研究員))
水俣病被害民の健康被害のあり方を再考しそれをふまえたケアの必要性という観点から考える。水俣学現地研究センターで毎月隔週火曜の健康・医療・福祉相談において、種々の属性を有する水俣病被害者たちの生活ニーズや疾病状況、医療ニーズをふまえたケアのありようについて聞き取りや検診を行った。次年度も引き続き健康・医療・福祉相談を行い、分析する予定である。
健康・医療・福祉相談は、水俣学現地研究センターなどにおいて13回開催し、延べ35人の方の相談を受け入れた。うち電話相談を2回行った。