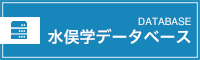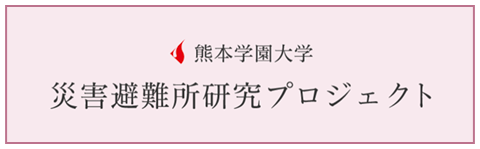2022年度
第一 水俣病被害の実態調査の継続
・調査設計とレジリエンス評価手法の開発(花田昌宣)
〇まず、現在、水俣病に関連して進められている被害者救済、地域振興策、自然生態系や環境汚染の全体像を資料に基づいて明らかにする。それに対する調査の手法、評価基準、実施体制に関する研究会を集中的に行い、調査の具体的手段、方法を確定し、夏以降、水俣地域において調査実施した。
・不知火海沿岸地域の漁村における生業調査と健康被害調査(井上ゆかり)(研究協力者:下地明友(医師・水俣学研究センター顧問・客員研究員))
〇漁村ごとに漁法も魚種も漁業形態も異なることに着目し、漁民の生業と健康被害の状況およびその連関を調査、被害の受容およびその社会的背景を明確にする。漁民の社会関与がレジリエンスの要素をなすからである。各種漁業資料と漁業者のヒアリングを重ねた。
・健康と生活被害実態の検討(田尻雅美)(研究協力者:伊東紀美代(水俣病協働センター・水俣学研究センター客員研究員))
〇水俣病被害民の健康被害のあり方を再考しそれをふまえたケアの必要性という観点から考える。本年度も引き続き、種々の属性を有する水俣病被害者たち(在宅療養者、通所サービス利用者、入所施設利用者、医療機関入院者)の、生活ニーズや疾病状況、医療ニーズをふまえたケアのありようと課題を、訪問調査による聞き取り、検診などを通して行った。健康・医療・福祉相談事業と胎児性・小児性水俣病患者の被害の把握
〇現地研究センターにおける健康・医療・福祉相談事業は原田先生によって始められ、下地先生が継続している。地元の被害者組織らと協力しながら進めており、本年も継続して行った。本事業に寄せられる相談内容は、自身が抱える種々の症状が水俣病からくるものかそうでないのか、介護問題など多岐にわたる。また、相談者は不知火海沿岸住民(現在は関東や関西圏に居住する人含む)で、年齢層も様々である。協力している主な客員研究員は伊東氏・谷氏である。
〇とりわけ、基盤研究(C)「胎児性・小児性水俣病患者の自立生活と主体形成への回路」(研究代表田㞍雅美、2020-2023年度)において、胎児性・小児性水俣病患者がおかれている被害実態、福祉的課題の調査研究をさらに進めた。
〇本年度は水俣学現地研究センターなどにおいて23回開催し、延べ28人の方の相談を受け入れた。うち電話相談を4回行った。