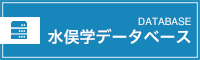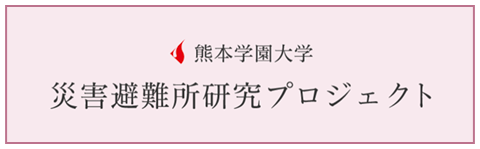2022年度
第二 地域発展と環境調査事業
・生態系環境調査・生活中の重金属分析(中地重晴)(研究協力者:エコネットみなまた)
水俣地域の市民の研究団体である「みなまた地域研究会」と共同して、地域における生業と環境汚染の市民調査を実施し、水俣病をふまえた水俣地域の未来を考える活動を実施してきた。この市民協働を発展させ、環境汚染の実態を客観化するために、住民の食生活を通した水銀の摂取状況を調査する。
海の幸を主とする住民の日常の食事を回収し水銀含有量を測定するとともに、毛髪水銀調査によって日常生活における人体への汚染の現状を明らかにする。事業報告書で報告したように、過去のデータは水俣学研究センターに蓄積があるためこの分析を急ぐ。あわせて土壌、水質あるいは魚介類の水銀分析を実施する。こうした生活環境における水銀汚染の現状把握が政策提言の客観的根拠を提供し、汚染サイトとしての水俣地域のリスク評価に対し、水俣社会がどのような取り組みを行うのか参与観察を行う。
共同研究の対象である「みなまた地域研究会」や水俣の市民団体の興味関心、活動のテーマが、水俣、伊佐、出水市にまたがる巨大風力発電建設計画((仮称)肥薩ウインドファーム))に移っており、水俣のまちづくりを考えるうえで、重要な取組みであるため、風力発電計画の問題点の整理に協力した。当研究センター主催の2022年度のテーマにとりあげ、「いのちと環境を考える~水俣・芦北に風力発電は必要か~」、エコネットみなまたを会場にハイブリッド方式で開催した。風力発電計画が全国的に立てられているため、水俣・芦北地域だけでなく、関東や関西、北海道からも受講される方がおられた。さらに、巨大風力発電計画の問題点や環境影響評価手続きについて、水俣病事件研究交流集会で報告するとともに、東京水俣病を告発する会の学習会で、講演し、水俣市民の風力発電に反対する活動に協力している。
・汚染サイトとしての水俣市周辺地域の評価の検討(中地重晴)
「水銀に関する水俣条約」で規定する汚染サイトの修復に関連して、エコパーク水俣湾埋立地及び、チッソの産廃最終処分場である旧八幡残渣プールに隣接する海岸埋め立て計画(水俣川河口部振興構想)について、リスク評価を行い、問題点を整理する作業を行う。あわせて、前述した「みなまた地域研究会」と連携して、水俣市周辺の環境汚染について、再評価する調査研究を行う。
コロナ禍で、調査は実施できなかったが、旧八幡残渣プールに隣接する海岸埋め立て計画(水俣川河口部振興構想)については、進捗を点検し、住民による行政不服の申し立てについて協力している。
・自然資本を最大限に活用したレジリエントで持続可能水俣・芦北地域の再構築(宮北隆志・中地重晴)
水俣市周辺に予定されている大規模風力発電所(4事業者、総計64基)の建設計画に伴う環境、並びに健康影響に関して問題点については、(仮称)肥薩ウインドファームを中心に整理・提示する作業を公開講座や水俣病事件研究集会を通じて行った。その際、大規模開発と地域における分散型エネルギー自給・自立の在り方についての再生可能エネルギーのガバナンスという視点からも問題提起した。
・「水俣・芦北地域戦略プラットフォーム」の活動・「ゼロ・ウェイスト円卓会議」への参与観察(藤本延啓)
2006年に開始した「水俣・芦北地域戦略プラットフォーム」の活動、および2008年より開催されている「ゼロ・ウェイスト円卓会議」への参与観察については、コロナ禍の影響もあり、今年度は実施できなかったが、藤本が「ゼロ・ウェイスト円卓会議」に関する経緯を整理・分析し論文にまとめた。