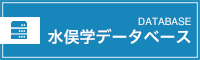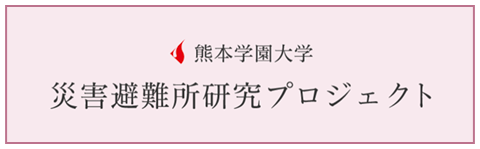第22期公開講座「水俣学研究センター20年~水俣学と公害のこれまでとこれから~」
第22期公開講座「水俣学研究センター20年~水俣学と公害のこれまでとこれから~」を開催いたします
〇「負の遺産としての公害、⽔俣病を未来に活かす」ことを⽬的として、私たちが⽔俣学研究センターを設⽴してから20年が経ちます。今回はあらためてその理念に⽴ち戻って、「⽔俣学と公害のこれまでとこれから」と題する公開講座を企画しました。
〇⽇本全国・世界各地で、今もなお多くの公害・環境問題の被害者が、「問題の解決」というにはほど遠い状況に置かれています。また、差別や偏⾒も根強く残っています。被害の当事者の⽅々、⻑く公害研究・活動に携わってきた⽅々のお話を聞きながら、みなさんと⼀緒に考える機会としたいと思います。どうぞご参加ください。開催日程:2025年9月30日から10月28日の毎週火曜
〇会 場:エコネットみなまた(熊本県⽔俣市南福寺60)『カーナビ入力時は、1-60と入力してください』
〇時 間:午後6時30分〜8時30分
〇対 象:水俣・芦北地域の市民(どなたでも、ご参加できます)
〇後 援:水俣市社会福祉協議会
〇開催方法:対面公開講座予定
〇9月30日 「⽔俣学研究センター20年 ―⽔俣学と⽔俣病―」 花田昌宣(熊本学園大学水俣学研究センター顧問)
〇10月7日 「判決から53年 ―「四⽇市公害」の今」 伊藤 三男 (四⽇市再⽣「公害市⺠塾」代表)
〇10月14日 「⽣まれなかったいのちについて」 頼藤 貴志( 岡⼭⼤学⼤学院 医⻭薬学総合研究科 疫学・衛⽣学分野 教授)
〇10月21日 「⽔俣病と知らなかった」 ⼤⼾迫 智 (⽔俣病被害市⺠の会(⽔俣病認定義務付け訴訟原告))
〇〇〇〇/〇〇「⽔俣病被害者と障害者」 東 俊裕 (元弁護士(溝口訴訟担当)、元内閣府参与)
〇10月28日 「なぜいまさらカネミ油症事件なのか」 三苫 哲也 (カネミ油症被害者全国連絡会 事務局⻑)詳細は案内チラシもご覧ください。
〇お申し込みは関連資料の申し込み用紙にご記入の上、お申し込みください。
◎参加申込先
〇熊本学園大学 水俣学現地研究センター
〇メール:m-genchi@kumagaku.ac.jp
〇Fax:0966-83-8883
〇電 話:0966-63-5030
公開講座の開催スケジュール
第21期公開講座「つくりたい水俣の未来を考える」を開催いたします
第21期公開講座「つくりたい水俣の未来を考える」◎
〇現在~2050年の日本社会は、少子高齢社会にともなう人口減少、地域社会の衰退や既存の産業構造の急激な変化、そして気候変動など地球規模の課題に直面しています。これらの問題は水俣市にとっても決して無関係ではありません。
〇受け身で「やがて来る水俣の将来」を受け入れるのではなく、私たち一人ひとりの課題として、ともに「つくりたい水俣の未来」像を考え、実現するためのヒントとなる内容を、農林水産業、福祉、エネルギー問題、子育て、公害・環境教育など、各分野の研究者や実践者に講演していただきます。
開催日程:2024年10⽉1⽇ から10⽉22⽇ の 毎週⽕曜⽇
会 場:エコネットみなまた(熊本県⽔俣市南福寺60)
時 間:午後6時30分〜8時30分
対 象:水俣・芦北地域の市民(どなたでも、ご参加できます)
後 援:水俣市、水俣市教育委員会、水俣市社会福祉協議会
開催方法:対面公開講座予定
10月1日 「『水俣』を学ぶ/学ばせる意味~広島女学院高校Global Issuesにおける取組から」
〇〇〇〇〇加藤 弘輝(広島女学院中学高等学校教諭)
10月8日 「森と棚田のめぐみはタダで良かですか?」
〇〇〇〇〇沢畑 亨(水俣市久木野ふるさとセンター愛林館館長)
10月15日 「環境福祉政策からのまちづくり~水俣の未来~」
〇〇〇〇〇炭谷 茂(恩賜財団済生会理事長)
10月22日 「里山(の保育)で育つ子どもは、安心としあわせに満ちみちて」
〇〇〇〇〇宮里 六郎(熊本学園大学名誉教授)*第5回目は講師の体調不良により、中止となります。
そのため全4回の開催となります。
ご了承くださいますよう、お願い申しあげます。詳細は案内チラシもご覧ください。
お申し込みは関連資料の申し込み用紙にご記入の上、お申し込みください。◎参加申込先
熊本学園大学 水俣学現地研究センター
メール:m-genchi@kumagaku.ac.jp Fax:0966-83-8883
電話0966-63-5030
第20期公開講座 「次世代に事実(教訓)をどう伝えるのか」配布資料
第20期公開講座 「次世代に事実(教訓)をどう伝えるのか」配布資料
10月3日「「来民開拓団の真相」に学びながら、「開拓慰霊祭のこころ」
を受け継ぐ子どもたち ~部落差別の現実に学び、反差別のなかまづくりへ~」
10月10日 「人間の尊厳を取り戻す闘い -水俣病事件 父からの伝言-」
10月17日 「次世代に長崎の被爆体験をどう伝えるのか」
10月24日 「ウトロで生きる ウトロで出会う~差別と歴史問題を乗り越えた力~」
10月31日 「セウォル号事件の記憶」
*公開講座当日のみ、閲覧できます。
第20期公開講座 「次世代に事実(教訓)をどう伝えるのか」のご案内
第20期公開講座「次世代に事実(教訓)をどう伝えるのか」
◎今年は、水俣病第一次訴訟判決から50年を迎えました。水俣病被害者の補償、救済問題は解決したとは言えません。水俣病の教訓を学ぼうとしても、被害当事者が高齢化し、話を聞くことも難しくなってきました。同様のことが、戦争被害や他の公害被害でも、当事者が高齢化し、起こったことの真相をどのように語り継いでいくのかが、課題になっています。
◎沖縄や広島、長崎では、高校生などが施設を案内する取り組み、若い語り部の養成が進められてきています。
また、関東大震災や満蒙開拓団などの経験、忘れ去られた事実を掘り起こし、事件を語り継ぐ取り組みも行われています。こうした取り組みの経験を学び、改めて、水俣病の教訓をどう語り継いでいくのか、考えていきたいと思います。
開催日程:2023年10⽉3⽇ から10⽉31⽇ の 毎週⽕曜⽇
会 場:エコネットみなまた(熊本県⽔俣市南福寺60)
時 間:午後6時30分〜8時30分
対 象:水俣・芦北地域の市民(どなたでも、ご参加できます)
後 援:、水俣市社会福祉協議会
開催方法:ZOOMを用いたハイブリッド方式公開講座予定
10月3日 「『来民開拓団の真相』に学びながら、『開拓慰霊祭のこころ』を受け継ぐ子どもたち ~部落差別の現実に学び、反差別のなかまづくりへ~」
◎森山英治( 熊本県人権教育研究協議会 顧問 旧満州来民開拓団遺族会 会長)
10月10日 「人間の尊厳を取り戻す闘い -水俣病事件 父からの伝言-」
◎川本愛一郎 (有限会社 リハシップ あい 代表取締役 水俣市立水俣病資料館 語り部)
10月17日 「次世代に長崎の被爆体験をどう伝えるのか」
◎林田 光弘 (長崎大学 RECNA特任研究員)
10月24日 「『ウトロで生きる ウトロで出会う』~差別と歴史問題を乗り越えた力~」
◎金 秀煥(キム・スファン) (ウトロ平和祈念館 副館長)
10月31日 「セウオル号事件の記憶」
◎金 翼漢(キム・イッカン)(韓国・明知大学 名誉教授(株)文化製作所可能性 代表理事)◎オンライン参加申込先
https://forms.gle/4pTJXTA5M76nLwuX9
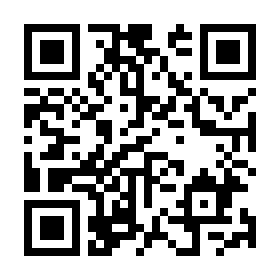
*当日のZOOMのURLは、上記申し込みフォームにございます。
*FAX・メールでのオンライン参加申し込みはできませんのでご注意ください。
*オンライン参加については当日まで受け付けます。◎会場参加申込先
熊本学園大学 水俣学現地研究センター
メール:m-genchi@kumagaku.ac.jp、FAX:0966-83-8883
電話0966-63-5030
第19期公開講座「いのちと環境を考える~水俣・芦北に風力発電は必要か~」のご案内
第19期公開講座「いのちと環境を考える~水俣・芦北に風力発電は必要か~」
現在、水俣周辺に三か所((仮称)大関山風力発電所、(仮称)肥薩ウインドファーム、出水水俣ウィンドファーム) の大規模風力発電計画が持ち上がり、事業者による環境影響評価の手続きが進められてきています。山間部に大型の風力発電塔を設置することで、大雨による土砂災害のリスクが高まります。低周波騒音による住民への健康被害の可能性、バードストライクによる野鳥や生態系への悪影響等が懸念され、周辺住民のいのちと環境が脅かされています。
巨大な風車で発電された電力は全量都市部に送られ、エネルギーの地産地消とはなりません。かつて、水俣の山間部に計画された産業廃棄物最終処分場問題とも共通する地元のためではなく大都会のための計画といえるでしょう。再生可能なエネルギーということで受け入れられるのかどうか、現在進行している三社の風力発電計画の課題を検証することを目的として開催します。
開催日程:2022年 9⽉27⽇ から10⽉25⽇ の 毎週⽕曜⽇
会 場:エコネットみなまた(熊本県⽔俣市南福寺60)
時 間:午後6時30分〜8時30分
対 象:水俣・芦北地域の市民(どなたでも、ご参加できます)
後 援:水俣市(依頼中)
◎講義日程と講師
9月27日 「日本のエネルギー・環境政策と再生可能エネルギー」
〇〇〇〇〇大島 堅一氏(龍谷大学教授)
10月4日 「水俣の自然(地形・地質及び動物)と風力発電問題」
〇〇〇〇〇長峰 智氏(日本地質学会会員)
10月11日 「風力発電による健康障害-低周波騒音について」
〇〇〇〇〇松井 利仁氏(北海道大学教授)*オンライン講義
10月18日 「みなまたに風車はいらない」
〇〇〇〇〇水俣・芦北住民からの報告(中村 雄幸氏(ちょっと待った風力発電の会)、ちょっと待った!出水風力発電の会、ちょっと待った!伊佐巨大風力発電の会、大関山を守る会)
10月25日 「カーボンニュートラルと水俣での大規模風力発電を考える」
〇〇〇〇〇中地 重晴(熊本学園大学社会福祉学部教授・水俣学現地研究センター長)
*新型コロナウイルス感染の状況によっては、講師が来場せずに遠隔で講演を行う場合もございますのでご了承ください。変更等については、ホームページ上に掲載いたしますのでご確認ください。
*オンライン(ZOOM)受講を希望される方は、申込書に必ずメールアドレスをご記入下さい。毎講義前にURLを送信いたします。
*出席の際は、マスクの着用をお願いいたします。
*発熱や咳等、風邪の症状がある場合は、参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。
◎受講を希望される方は、関連資料の申し込み用紙に必要事項を記入の上、
メール:m-genchi@kumagaku.ac.jp、FAX:0966-83-8883にお送りください。
電話0966-63-5030でも受け付けています。
第18期公開講座「新型コロナウイルス感染症に翻弄される暮らしと社会:私たちはどのような未来を選択しようとしているのか?」のご案内
2021年度熊本学園大学水俣学研究センター 第18期公開講座「新型コロナウイルス感染症に翻弄される暮らしと社会:私たちはどのような未来を選択しようとしているのか?」を開催いたします。
2020年3⽉のパンデミック宣⾔(WHO)から1年半、新型コロナウイルス(SARS-Cov-2)による未知の感染症(COVID-19)は、世界中に蔓延し(確認された感染者は1億9000万⼈を超え、死者は400万⼈を上回る:7⽉19⽇現在)、未だに終息への道筋は⾒えてこない。未知のウイルスは、変異を繰り返す中で感染⼒を⾼めつつあり、その起源、⼈への感染ルートの解明もなされない中で、社会的格差が拡⼤し、「貧困」の固定化が進⾏している。
昨秋に続く今年度の公開講座では、この1年あまりの間にあぶり出されてきた諸課題をみんなで確認・共有し、「今を⽣きる私たちに、また社会に求められているものは何か」についての議論を深め、⼈と⼈・⽣き物、そして健全な⽣態系全体とのつながりをより豊かにしていくための⽅策について、⽔俣・芦北地域から発信していきたい。
開催日程:2021年 9⽉28⽇ から10⽉26⽇ の 毎週⽕曜⽇
会 場:エコネットみなまた(熊本県⽔俣市南福寺60)
時 間:午後6時30分〜8時30分
対 象:水俣・芦北地域の市民(どなたでも、ご参加できます)
後 援:水俣市、水俣市教育委員会
◎講義日程と講師
9月28日 「新型コロナウイルス対策これまでとこれから」
〇〇〇〇〇和⽥ 耕治(国際医療福祉⼤学医学部公衆衛⽣学 教授/厚⽣労働省専⾨家会議疫学班)
10月5日 「新型コロナ対策の疫学的検討」
〇〇〇〇〇緒⽅ 剛 (茨城県潮来保健所⻑/⽇本公衆衛⽣学会感染症対策委員)
10月12日 「政令指定都市の保健所での取組を振り返って」
〇〇〇〇〇⾼本 佳代⼦ (宮崎県⽴看護⼤学 講師/元熊本市保健衛⽣部⻑ 統括保健師)
「今だからこそ考えよう、持続可能でレジリエントな暮らしと社会」
〇〇〇〇〇宮北 隆志 (熊本学園⼤学社会福祉学部 教授/水俣学現地研究センター長)
10月19日 「熊本県の県型保健所におけるコロナ対応」
〇〇〇〇〇劔 陽⼦ (菊池保健所⻑/県北広域本部保健環境福祉部⻑/菊池福祉事務所⻑)
10月26日 「感染症と⼈権―新型コロナウイルス感染症をめぐる差別―」
〇〇〇〇〇⽮野 治世美 (熊本学園⼤学社会福祉学部 准教授/水俣学研究センター研究員)
*新型コロナウイルス感染の状況によっては、講師が来場せずに遠隔で講演を行う場合もございますのでご了承ください。変更等については、ホームページ上に掲載いたしますのでご確認ください。
*今期より、毎回、オンライン(ZOOM)での受講が可能となりました。
*オンライン(ZOOM)受講を希望される方は、申込書に必ずメールアドレスをご記入下さい。毎講義前にURLを送信いたします。
*出席の際は、マスクの着用をお願いいたします。
*発熱や咳等、風邪の症状がある場合は、参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。◎受講を希望される方は、参考資料の申し込み用紙に必要事項を記入の上、
メール:m-genchi@kumagaku.ac.jp、FAX:0966-83-8883にお送りください。
電話0966-63-5030でも受け付けています。
第17期公開講座「コロナ禍との闘い ウイルスとの共生 -アフターコロナの生き方、社会のあり様を見据えて」のご案内
2020年度 熊本学園大学水俣学研究センター 第17期公開講座「コロナ禍との闘い ウイルスとの共生 -アフターコロナの生き方、社会のあり様を見据えて」を開催いたします。
今回の公開講座では、「感染症」と向き合ってきた⻑い歴史の中で、「いま何が起きているのか」「何を学ぶことができるのか」「今をいきる私たちに、また社会に突きつけられているものは何か」について、共に学び、考え、議論していきたいと思います。
開講日:2020年9月29日から10月27日の毎週火曜日
場 所:エコネットみなまた(水俣市 南福寺60番地 0966-63-5408)(ロッキー南福寺隣)
時 間:18:30~20:30
対 象:水俣・芦北地域の市民(どなたでも、ご参加できます)
後 援:水俣市、水俣市教育委員会
◎講義日程と講師
〇9月29日「未知の”感染症”にどう向き合っていくのか 〜ワンヘルス(One Health)の視点から〜」
〇〇宮北隆志 (水俣学現地研究センター長、熊本学園⼤学社会福祉学部 教授)
〇10月6日「新型コロナウイルス対策〜これまでとこれから〜」
〇〇和⽥耕治 (国際医療福祉⼤学 教授)*オンライン講演
〇10月13日「感染症の洋の東⻄:コロナ自粛の経済学」
〇〇花⽥昌宣 (水俣学研究センター長、熊本学園⼤学社会福祉学部 教授)
〇10月20日
「新型コロナ感染症 熊本県下の動向」
〇〇宮北隆志(水俣学現地研究センター長、 熊本学園⼤学社会福祉学部 教授)
「新型コロナ感染症の予防と対策︓開業医の⽴場から」
〇〇髙野義久 (たかの呼吸器科内科クリニック 院⻑)
〇10月27日「新型コロナウイルス感染症と日々の暮らし」
〇〇水俣市の民生委員、介護支援専門員、調剤薬局経営者、こども園園長
*2020年8月18日、一部講師とタイトルが変更になりました。
*新型コロナウイルス感染の状況によっては、 全て会場でのオンライン講演となる場合もあります
*受講はすべて無料です。全講義受講者には修了証を発⾏します
*出席の際は、マスクの着用をお願いいたします。
*会場ではヘルスチェックシートのご記入をお願い致します。◎受講を希望される方は、参考資料の申し込み用紙に必要事項を記入の上、
メール:m-genchi@kumagaku.ac.jp、FAX:0966-83-8883にお送りください。電話0966-63-5030でも受け付けています。
第16期公開講座 「『ひきこもり』を知る・考える -『個人の問題』で片づけてしまわないために-」のご案内
2019年度 熊本学園大学水俣学研究センター 第16期公開講座 「『ひきこもり』を知る・考える -『個人の問題』で片づけてしまわないために-」を開催いたします。
今回は「『ひきこもり』を知る・考える-『個人の問題』で片づけてしまわないために-」と題し、「ひきこもり」を「個人の問題」としてではなく、「社会の問題」として考えていけるよう、様々な分野の方にお話をしていただきます。開講日:2019年9月24日~10月15日 毎週火曜日
時 間:18:30~20:30
場 所:水俣市公民館
対 象:水俣・芦北地域の市民
後 援:水俣市教育委員会
〇講義日程と講師
9月24日 「『ひきこもり』が問いかけるもの」
〇〇〇〇〇〇富田正徳氏 (熊本県ひきこもり地域支援センター 所長)・西田 稔氏 (同センター 参事)
10月1日 「国際調査で見えてきた『ひきこもり』の課題-なぜひきこもりは日本に多いのか?-」
〇〇〇〇〇〇加藤隆弘氏 (九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 講師)
10月8日 「児童・思春期外来を通して考える『ひきこもり』支援」
〇〇〇〇〇〇城野 匡氏 (熊本学園大学社会福祉学部教授・医師)
10月15日 「水俣市社会福祉協議会におけるひきこもり支援」
〇〇〇〇〇〇秋山真輝氏 (水俣市社会福祉協議会 主任相談支援員)受講はすべて無料です。
全講義受講者には修了証を発行いたします。
関心のある回のみの参加も可能です。お申込み・お問い合わせ先
熊本学園大学水俣学現地研究センター
Tel:0966-63-5030 Fax:0966-83-8883
E-mail:m-genchi@kumagaku.ac.jp
第15期公開講座「負の歴史をどう語り継ぐのか~次世代による負の遺産の伝承とは~」のご案内
2018年度 熊本学園大学水俣学研究センター第15期公開講座「負の歴史をどう語り継ぐのか~次世代による負の遺産の伝承とは~」を開催いたします。
〇戦争、原爆、水俣など経験した世代が高齢化し、経験者、被害者の多くが亡くなってきています。人類が経験したこと、負の歴史を次世代にどう語り継ぐのかが、各地で問題になってきています。たとえば、沖縄戦、ひめゆり部隊の経験を子供の世代が語り部として、見学者を案内するようになってきました。水俣病資料館でも、第一次訴訟の原告や認定患者の語り部は高齢で引退し、家族が代わって語り部として語るようになってきています。
負の遺産として、公害や戦争被害の経験や教訓をどのように語り継ぐのか、各地の取り組みを聞く中で、水俣病被害をどのように次世代に伝えていくのかを、水俣市民とともに考えていきたいと思います。期 間:2018年10月2日から10月30日までの毎週火曜
時 間:18:30~20:30
会 場:水俣市公民館第1研修室(水俣市浜町2丁目10番26号)
後 援:水俣市教育委員会〇講義日程と講師
10月 2日 「沖縄戦を語り継いでいく具体的な提案 〜”伝え手”となってもらう平和学習実践〜」 国仲 瞬 (株式会社 がちゆん 代表取締役)
10月 9日 「四日市公害から学んだこと。今、私たちにできること。」 谷崎仁美 (自然観察指導員三重連絡会 事務局長)
10月16日 「被爆二世として生きる」 寺中正樹 (山口被爆二世の会代表)
10月23日 「あおぞら財団の活動と公害経験を伝えること」 村松昭夫 (あおぞら財団理事長・弁護士)
10月30日 「水俣病を学び伝えていく~あやまちを繰り返さない主権者となるために~」 高木 実 (水俣芦北公害研究サークル・熊本学園水俣学研究センター客員研究員)受講はすべて無料です。
全講義受講者には修了証を発行いたします。
関心のある回のみの参加も可能です。お申込み・お問い合わせ先
熊本学園大学水俣学現地研究センター
Tel:0966-63-5030 Fax:0966-83-8883
E-mail:m-genchi@kumagaku.ac.jp
第14期公開講座「払っているだけの介護保険?はじめの一歩」のご案内
2017年度 熊本学園大学水俣学研究センター第14期公開講座「払っているだけの介護保険?はじめの一歩」を開催いたします。
2000年から施行された介護保険。介護は「突然」に・・・とよく聞きますが本当にそうでしょうか。水俣市では本年度から介護保険改正に伴う総合支援事業が開始されていますが、その内容をご存じですか。水俣市の高齢化率は34.83%、15歳から64歳までの生産年齢人口の構成比は53.48%(2015年4月現在)で、団塊世代が75歳以上となる2025年以降は医療や介護のさらなる需要増加が見込まれています。さらに水俣市では、水俣病公式確認から61年を迎え、患者の平均年齢が77.7歳(NHK2017年5月1日報道)となった今年、水俣病患者の抱える介護および地域福祉の課題も具体的に検討していかなければなりません。
こうした状況をふまえて、「突然」迎える介護ではなく、もう必要かもしれない介護をともに考えていきたいと思います。介護保険、はじめの一歩を踏み出してみませんか。期 間:2017年9月26日から10月24日までの毎週火曜
時 間:18:30~20:30
会 場:水俣市公民館第1研修室、10月17日のみ第2研修室
後 援:水俣市、水俣市社会福祉協議会、水俣市教育委員会講義日程と講師
9月26日 「社会保険の発展と社会保障―日独比較の視点からー)」 松本勝明(熊本学園大学社会福祉学部 教授)
10月3日 「住民でつくる介護予防と生活支援~ささえりあ帯山の実践を通して~」 那須久史(熊本市高齢者支援センターささえりあ帯山 センター長)
10月10日 「水俣市における介護保険―水俣市民と水俣病患者の現状と課題」 秋山真輝(社会福祉法人水俣市社会福祉協議会 社会活動専門員)
10月17日 「認知症の人と家族を支える地域づくりを考える」 黒木邦弘(熊本学園大学社会福祉学部 准教授)
10月24日 「病と関わりをめぐって:認知症、アルコール依存症、うつ病―ケアの場は星座のごとく-」 下地明友(熊本学園大学社会福祉学部 教授、医師)受講はすべて無料です。
全講義受講者には修了証を発行いたします。
関連資料の案内チラシもご覧ください。お申込み・お問い合わせ先
熊本学園大学水俣学現地研究センター
Tel:0966-63-5030 Fax:0966-83-8883
E-mail:m-genchi@kumagaku.ac.jp