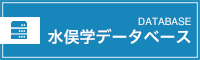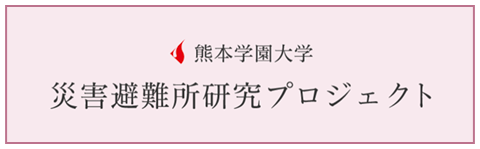2023年度
第1班<健康とケア>研究プロジェクト
〇未だ認定申請者がいるなかで被害の現状と高齢化する患者たちの抱える福祉的課題を明確にするために被害当事者のケアおよび健康調査を行った。また下記のとおり成果報告を行った。
・2023年8月に井上が「経済成長最優先の陰で放置された公害―公害被害者に経済学はどう向き合うか」「新自由主義と闘った巨人、〇宇沢弘文―『人間のための経済学』はどう構想されたのか」PARC自由学校ハイブリッド読書ゼミ、特定非営利活動法人アジア太平洋資料センターにて報告した。
・2023年12月に井上が「一次訴訟判決後から現在までの水俣病被害当事者の『かき消されゆく声』」同時代史学会2023年度大会「安定化させる力学とかき消されていく声ー1970年代の水俣から考えるー」東京経済大学にて報告した。
・2023年田㞍が「水俣病問題の歴史と現在」2023年度部落解放・人権講座で報告した。
・2024年田㞍と井上、佐藤英樹・佐藤スエミが「水俣病問題」差別禁止法研究会第5回「差別禁止法を求める当事者の集い」で報告した。健康・医療・福祉相談事業と胎児性・小児性水俣病患者の被害の把握
〇現地研究センターにおける健康・医療・福祉相談事業は原田先生によって始められ、下地先生が継続している。地元の被害者組織らと協力しながら進めており、本年も継続して行った。本事業に寄せられる相談内容は、自身が抱える種々の症状が水俣病からくるものかそうでないのか、介護問題など多岐にわたる。また、相談者は不知火海沿岸住民(現在は関東や関西圏に居住する人含む)で、年齢層も様々である。協力している主な客員研究員は伊東氏・谷氏である。
〇とりわけ、基盤研究(C)「胎児性・小児性水俣病患者の自立生活と主体形成への回路」(研究代表田㞍雅美、2020-2023年度)において、胎児性・小児性水俣病患者がおかれている被害実態、福祉的課題の調査研究をさらに進めた。
〇本年度は水俣学現地研究センターにおいて34回開催し、延べ52人の方のうち電話相談を9回、大学センターでは7回行い、延べ7人の方のうち電話相談を6回、合計41件、延べ59人の相談を受け入れた。